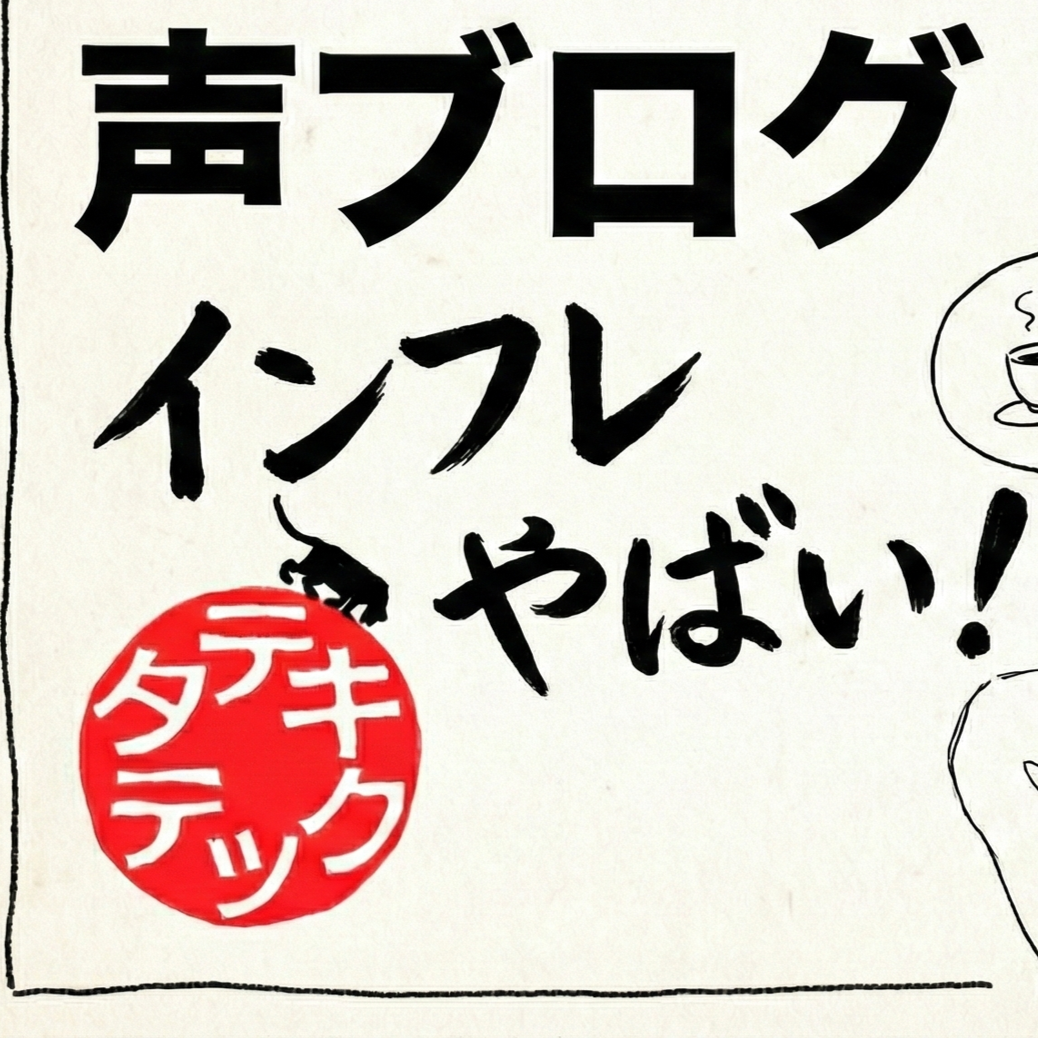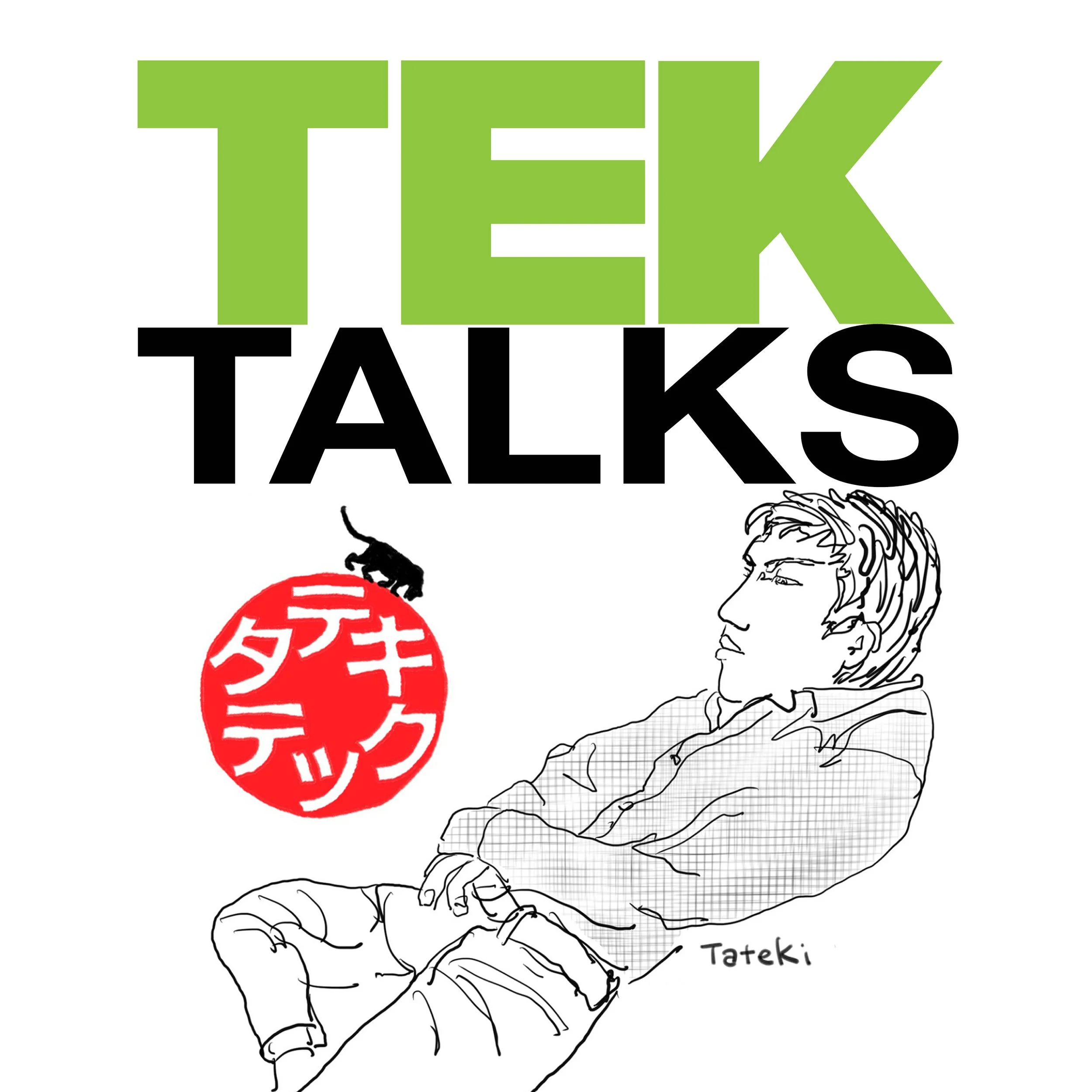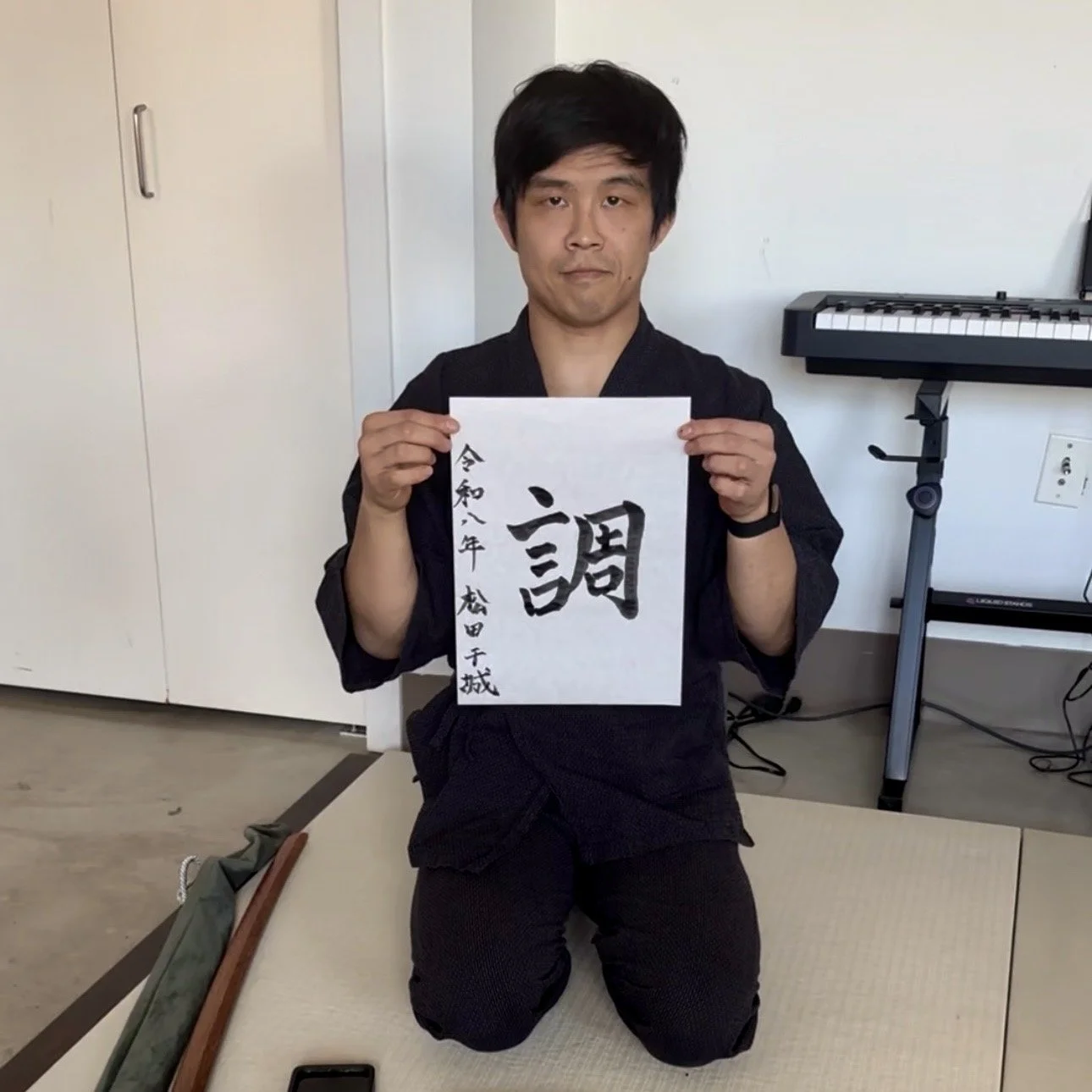ベン=グリーンフィールド 東京滞在 #3
DAY3
前回までのあらすじ
日本人としてこの上ない幸せです。今日は国技館で着物を着て9月場所を升席から観戦しました。その後はちゃんこ発祥の地、両国でちゃんこを食べました。貴乃花部屋のご支援がなければ実現しませんでした。横綱ギフトにも感動です。本当に感謝!ベンも喜んでくれました。
昨日に引き続き、今日も奇跡が起こりました!以前、お仕事でご一緒させていただいた貴乃花親方のご好意により、幸いにも余っていた枡席を手配していただきました。人気な9月場所のチケットを入手することは簡単ではありません。場所2日目の今日は「和装に身を包み相撲を観戦する」という新たな視点で、大相撲の楽しさと感動を体験して頂けるイベント「和装デイ」でした。背の高いベンのサイズがあるか心配でしたが、無事に高身長サイズの着物を用意してくれました。
9月なので着物は時期的に単衣ですが、日本は暑い暑い!特に日本の湿気はエグかったです。寄席や大相撲観戦に着物で出かけるのは、粋そのもの。せっかくですから、次はタテキ妻も連れて来て、お気に入りの着物で楽しみたいですね。アメリカ人がブリンブリンを装着してカーネギーホールのVIP席から鑑賞するというステータスと一緒か?いや、マジで例えヘタクソ。もうよく分かりません。
着物は、当日会場の着付けスペースに用意されていて、好きな着物を選んだらその場で着付け師が着付けをしてくれます。着用していた服や荷物は、イベント終了まで会場で預かってもらえるので、貴重品だけ持って身軽に大相撲を観戦できるという点も魅力ですね。着物を持っている人や、自分で着付けができる人は、フリープランを選んでリーズナブルに大相撲を楽しむことも可能。このときのイベントは、先着で蚊帳ふきんのプレゼントもあったようなので、お得感満載でした。
やっぱり生で観ると迫力が違います!楽しかった!
Box seats for September Basho.
日本相撲協会公式のチケット販売サイト「チケット大相撲」や外部販売サイト「チケットぴあ」などでチケットの購入が可能です。チケット大相撲を使うと全ての席が購入可能(※溜席と自由席をのぞく)。また座席選択も可能(※抽選販売時かつ一部の席をのぞく)チケットぴあなど外部サイトだと購入できる席の種類は少なくなります。相撲協会が自前のサイトで買わせようとする意図を強力に感じる。お得かつ人気のあるチケットはもちろん「チケット大相撲」独占販売。
また「最速先行受付」で約2ヶ月前から一番最初に抽選販売をできるのも「チケット大相撲」です。
基本的に席は
タマリ席(溜席)
マス席(枡席)
イス席(椅子席)
3つのタイプがあります。 まず、土俵の真下で力士が転がり落ちてくる「タマリ席」(溜席)は飲食禁止、カメラ撮影禁止、小学生以下NGなどルールが厳しい。力士が突っ込んできてケガをしても自己責任のようです。格闘技だとリングサイドや金網サイドのVIP席ですね。
次がその席の後ろから始まる「マス席(枡席)」1~8列目が「マスA席」、9~12列目が「マスB席」、13~15列目が「マスC席」。土俵から離れるにつれ、価格が安くなっていきます。2階は全て椅子席で1~6列目が「イスA席」、7~11列目が「イスB席」、12~13列目が「イスC席」とランク分け。一番最後列の14列は1周分「自由席」です。
マスA席はやはり人気なので、チケットのその殆どを、お茶屋さん(相撲案内所)がおさえているようです。なので「チケット大相撲」の前売りでも、一般向けの発売は少ないそうです。また、マスA席ともなると常連のお客さんや法人のお客さんが全日通しでおさえているので、更に入手困難らしいです。
土俵上のタイムスケジュール
日本相撲協会 土俵上の時間割を参照
8:00: 国技館オープン
8:25頃〜 前相撲
入門したばかりの新弟子が取る相撲を前相撲といい、三日目(大阪場所は二日目)より行われます。
8:35頃~ 序ノ口~幕下取組
この時間から既に取組は始まっています。館内も静まり返った中で、 序ノ口、序二段、三段目、幕下力士らが明日の関取を目指して頑張っています。
12:50頃〜 新序出世披露
成績優秀者から順に出世し「新序出世披露」で翌場所序ノ口に上がる資格を得た力士を披露します。
14:15頃~ 十両土俵入り
化粧廻し姿の十両力士が堂々と登場。 関取と呼ばれ、化粧廻しを締め大銀杏を結い、相撲界で一人前と見なされるのは十両からです。
14:35頃~ 十両取組
幕内進出を狙う若武者や円熟した取り口のベテランが激突! 体つき、力士と力士がぶつかり合う時の音、迫力が違います。
協会ごあいさつ
初日・千秋楽に日本相撲協会理事長が三役以上の力士と一緒に土俵に上がり、お客様へご挨拶させていただきます。
15:40頃~ 幕内土俵入り
人気力士たちが色鮮やかな化粧廻しを締めて土俵を一周。相撲場の雰囲気が一気に華やぐ時間です。 土俵入りの順序は奇数日は東方から、偶数日は西方から土俵にあがります。
15:55頃~ 横綱土俵入り
横綱が右に太刀持ち、左に露払いを従え土俵入り。 柏手を打って四股を踏む横綱に客席からは「よいしょ!」の掛け声が。
中入り
横綱土俵入り終了後から幕内取組開始までの休憩時間。 立行司による、翌日の取組披露がございます。(進行状況により行われないこともあります)
16:10頃~ 幕内取組
いよいよ幕内取組です。 人気力士、強豪力士が次々と登場して、熱戦を展開! 17時過ぎには小結、関脇、大関も登場します。
17:15頃~ 三役揃い踏み※千秋楽のみ見られます
千秋楽では、結び三番を残して「三役揃い踏み」が行われます。 東西それぞれ三人の力士が土俵に上がり、扇の形で正面を向き三人そろって四股を踏む儀式に場内の雰囲気は最高潮に達します。
17:55頃~ 弓取式
結びの一番終了後、弓取りの力士が弓を華麗に振る儀式で、結びの一番の勝者に代わり行ないます。
表彰式※千秋楽のみ見られます
千秋楽には幕内優勝力士に天皇賜盃と優勝旗、また関脇以下で活躍した力士に 殊勲賞、敢闘賞、技能賞の三賞が授与されます。
両国国技館の相撲教習所で着物の着付け
両国国技館の中にある相撲教習所で着付けをしてもらいました。受付の方が元力士で色々お話を聞きました。新弟子は全員、相撲教習所に通うそうです。教習所では実技と教養に分けて、力士を教育・指導する場所だそうです。いわゆるレクチャーのような授業の他に、実技では四殷、鉄砲、殷割り、すり足、伸脚などの基本を学び、それを繰り返し稽古するそうです。新弟子は半年通うみたいです。
ベンの足デカ!
190cm近くあるベンの足は規格外のサイズ!タテキと比べると大人とキッズみたい(笑)







国技館の敷地内にある力士になるための学校で「和装」を装備!ジャパニーズkimonoに身を包みます。男性の着流しは襦袢、長着、帯、足袋、履物。草履はギリギリでしたがベンのサイズが見つかったそうです。9月は透けない生地の単衣仕立ての着物の季節です。新陳代謝の高い野郎たちにとって日本の湿気+Tシャツ短パンに比べると厚着の着物は地獄でしたが、しっかり着こなして着付け師に褒められて痩せ我慢。
脚の長いベンはドカドカと大股で歩くので着崩れしてしまうことを恐れて「歩き方指導」しました。「郷に入れば郷に従え」の強制w。そのまま着物を着たら情緒たっぷりの雰囲気が味わえる相撲案内所入り口から入場しました。たっつけ袴姿の「出方さん」が出迎え、枡席まで案内してくれました。
国技館内には20軒の案内所があり、昔それぞれが屋号を持って「お茶屋」と呼ばれていました。江戸時代にさかのぼると、大相撲のほかに芝 居小屋や歌舞伎などにもお客様に代わって、入場券やお弁当など飲食の手配を引き受ける代行業として「お茶屋」制度がありました。現在は「お茶屋」ではなくて「案内所」と呼ばれます。出方さんに頼めば、飲み物から食事まで即座に届けてくれます。
お土産横綱セット
大相撲観戦のよい思い出となるお土産は館 内の売店でも販売していますが、案内所のお土産は一味違います。国技館の名物である焼き鳥(国技館内で焼かれた焼き鳥)をはじめ、売店には様々なグッズが販売されていますが、タテキとベンのお土産はトップオブザトップのお土産「横綱セット」。
枡席に座って横綱セットの中身を拝見!ちなみに枡席は4人用だが、現代人の体格では2人でも狭いw。パーソナルスペースを尊重する北欧の人だったら確実に1人用だな(笑)




食事 幕の内弁当、焼鳥、袋物、菓子又は煎餅、あんみつ、甘栗
飲み物 缶ビール、お茶
お土産 陶器、お菓子、煎餅、パンフレット
ベンは興奮してスナップチャットに横綱セットの中身をファンたちにライブで紹介。一つ一つ手に取り詳細を説明してたらアサヒビールを発見!「ビア!?」とビックリして爆笑。確かにアメリカのシーンではアルコールはIDチェックがマストですからね。弁当も名物焼き鳥も美味しかったです。陶器は思いがけない日本のお土産になりました。
相撲観戦の仕方
ルール
取組は両者の暗黙の了解で決まる『立ち合い』で開始される
手で使って良いのは手のひらだけ。拳で殴ったり肘打ちなどは反則となる
足はひっかけたり払ったりするのはOKだが、胸やお腹を蹴る行為(キック)はNG
頭突き/目やのどなどの急所を突く/故意にまげを掴む、といった行為は反則となる
勝敗は以下のいずれかによって決定
どちらか一方の体が土俵外に着地する
【例】相手の力士を土俵外に追い出したりした場合どちらか一方の足の裏以外が着地する
【例】土俵内で一方の選手を転倒させたりした場合反則行為を行った場合
【例】故意にまげを掴んだりボクシングのように握り拳で殴ってしまった場合
土俵
大相撲では、一辺が6.7メートルの正方形に土を盛り、その中央に直径4.55メートル(15尺)の円が俵で作られています。また、その円の東西南北4ヶ所に「徳俵」と呼ばれる、俵1つ分の出っ張りが設けられています。
土俵入り
大相撲の十両以上の力士が土俵の上で行う儀式のことです。 幕下力士は土俵入りできません。土俵入りは幕内力士と十両だけです。幕内土俵入りと言う場合、横綱を除く幕内力士の土俵入りです。横綱には特別に「横綱土俵入り」があります。幕内の土俵入りは行司が先導します。下位の力士から花道より入場します。東方力士は東の花道から、西方力士は西の花道からです。土俵入りが終わると、先頭の力士から順に土俵を降り、もと来た花道を退場します。行司は一番最後について行きます。
日によって土俵入りの順番が異なります。土俵入りの順番は奇数日が東方力士、偶数日が西方力士からとなっています。その日、東方から登場する力士が東方力士、西方から登場する力士が西方力士です。ちなみに番付の東西とは関係ありません。
花道を上ってくる力士の順番には決まりがあります。番付で上位の者ほど後の順番になります。対戦する力士の取組が毎日違うので、土俵入りする力士の顔触れも毎日違います。
幕内と十両の土俵入りは同じ作法です。
一列になって花道から土俵下まできて、場内アナウンスを待ちます。
場内アナウンスで紹介を受けた力士は一礼して二字口より土俵に上がります。「旭鷲山、モンゴル出身、大島部屋」のように四股名、出身地、所属部屋が呼び上げられます。
土俵に上がると、時計回りとは逆に土俵を一周します。内俵の外側に沿って歩きます。そして、所定の位置でお客さんのほうを向いて立ちます。つまり、土俵を背にして立ちます。
最後の力士(普通は、大関)が土俵に上がると、全員が土俵の内側に向き合います。
柏手を1回打ちます。
右手を上げます。
両手で化粧廻しの端をひょいと持ち上げます。
両手を上げます。
入場した順に土俵を降り、花道を引き上げます。
土俵入りの動作には意味があり、幕内の土俵入りは横綱土俵入りと同じ動作を簡略化したものです。
柏手を打ちます:
右手を上げます。3段構えの「上の構え」を表します。
両手で化粧廻しの端を持ち上げます。四股踏みを表します。
両手を上げます:四股踏みの終了を表します。
十両土俵入りは幕幕下上位の取組5番前で行います。
土俵入り
相撲は神事
土俵の上の吊り屋根の四隅にある4つの房を四房(しぶさ)といい、青,赤,白,黒の四色で,四季と四神(青龍、白虎、朱雀、玄武)を表します。
・黒い総 …… 玄武(げんぶ)
神は亀で、方角は北を向いています。
・赤い総 …… 朱雀(すざく)
神は鳥で、方角は南。
・緑の総 …… 青龍(しょうりゅう)
神は龍で、方角は東。
・白の総 …… 白虎(びゃっこ)
神は虎で、方角は西。
これら天の四神獣は土俵を守る意味で四隅に祀られているそうです。
横綱が土俵入りする前は客席も満員御礼!ベンと一緒に国技を楽しみました。
Dinner
両国に来て国技館で大相撲観戦した後は力士のソウルフード、ちゃんこ鍋を食べました。大将に聞いたらちゃんこって親子を意味するそうです「ちゃん」と「こ」でちゃんこ、弟子が親方と食べるからでしょうか?現代では現役を引退した力士がちゃんこ屋さんを開業するセカンドキャリアをよく耳にします。その草分けがこの昭和12年(1937年)創業の「ちゃんこ川崎」元関取であった力士横手山が、両国に自身の自慢のちゃんこを味わってもらえるよう店を出したことが始まりだそうです。
上記で説明した通り、手を土俵についたら負けてしまうのが相撲のルールですね。牛や豚は4足歩行なので縁起が悪いので、鶏肉オンリーが元祖ちゃんこ鍋のスタイルだそうです。
現在でもちゃんこ鍋は伝統の鶏出汁一本、両国に数あるちゃんこの店のなかでも最古の店として今でも多くのお客さんを自慢の出汁で唸らせています。創業当初とほとんど作り方を変えていないという伝統のちゃんこ鍋を体験してきました。
伝統の味を守り続ける1937年創業、ちゃんこ 川崎
Kawasaki also offers a number of chicken-based side dishes. You can pick and choose which of these you want with your nabe from the simple a la carte menu. But the easiest procedure is to order the all-in chanko course, which will give you a taste of everything. I and Ben ordered Chako-course. The owner, Kawasaki-san not only oversees everything and everyone as they come and go, he is also in charge of the small grill on which he prepares sticks of delectable yakitori. There are small patties of tsukune mince; chunks of white breast meat; and a selection of internal organs (chewy heart, soft liver, crunchy gizzard). He also doles out portions of basic chicken salad, and tori-wasa, rare chicken lightly flavored with piquante wasabi. Guess what? We tried everything!!
I and Ben are waiting for Chanko nabe getting ready
雨の中外で30分以上待ちました。お腹ペコペコで待った後でしたが、風情あふれる日本家屋のお店に入ると感動の方が強く、メニューもどうしようか迷っていると(いつもの英語が無いパターン)、「ちゃんこコース」を発見!前菜や焼き鳥がついてくるので2人前をオーダーしました。
代々引き継がれるソップ炊きのちゃんこ鍋は朝びきの新鮮な鶏ガラを使用し、6時間かけて炊いた出汁を醤油ベースの味で仕上げたスープです。また写真見ても分かる通り、年季の入った鍋が絶対マジックを引き起こしていると思います。鶏肉は適度な歯応えがあり、野菜や油揚げ、白滝等の具は、丁寧な下ごしらえを施しており、具材は庶民的だけど洗練された味でした。
コースの前菜は焼き鳥、鳥サラダ、鳥わさ、大きめのつくね。ベンはSumoレスラー達はチキンであんなにデカくなるのか?と不思議顔。カウンター席だったので、大将が鍋の食べ方を細かく教えてくれて本場の鍋奉行ってやつも体験しました。今日は大相撲を着物で観戦して、伝統、歴史ある老舗で元祖ちゃんこ鍋をいただいた貴重な日でした。
ちゃんこ川崎
〒130-0026
東京都墨田区両国2-13-1
03-3631-2529交通手段JR総武線 両国駅 西口 徒歩3分
営業時間 月~金 ディナー 17:00~22:00(L.O.21:00)
土 ディナー 17:00~21:30(L.O.20:30)
定休日 日曜日 祝日
ちゃんこ川崎
-
Private
1
- Jun 5, 2022 オフサイトイベント ヘルシンキ 2022
-
TEK Talks
60
- Jan 11, 2021 TEK Talks はじめました
- Jan 20, 2021 #2 タイでムエタイ修行:ロードワークに行く時はイシツブテを忘れずに
- Jan 21, 2021 #3 北米MMA:汚い話ですいません…試合会場はなんと…!
- Jan 22, 2021 #4 ブラジルで柔術修行:地球の裏側で○光中毒にされそうになった話
- Jan 23, 2021 #5 どうやってジゼル・ブンチェンのトレーナーになった? タノジョー砲炸裂...
- Jan 24, 2021 #6 パラグアイに寄り道:半袖短パンのおっちゃんの装備がチートすぎる件
- Jan 25, 2021 #7 スペイン:山奥のダウンタウンで野宿した後お湯に感動した話
- Jan 27, 2021 #8 フランス:ムーランルージュにて賄賂で解決…
- Jan 28, 2021 #9 フィンランド:ラップランドの迷いの森で全員凍死ゲームオーバー?
- Jan 29, 2021 #10 イタリア:心臓バクバクでヴェスパを返却
- Jan 31, 2021 #11 香港:重慶大厦(チョンキンマンション)に泊まる
- Feb 1, 2021 #12 タテキッチン:誕生日フルコース年に一度のペスカトーレ
- Feb 2, 2021 #13 アメリカ:イタリア人街でハイタッチのタイミングを外した訳
- Feb 3, 2021 #14 アルゼンチン:干城のアナザースカイ「悪魔の喉笛」
- Feb 4, 2021 #15 NesPicks:森喜朗氏「女性が…」発言について
- Feb 5, 2021 #16 ポッドキャスト収録後:みんな息吐こうぜ!
- Feb 6, 2021 #17 Clubhouse:逆カルチャーショックを乗り越える
- Feb 7, 2021 #18 Clubhouse:セクシー女優の部屋で大人の保健の話
- Feb 7, 2021 #19 スーパーボウル:日本にトムの凄さが伝わってほしい
- Feb 9, 2021 #20 Clubhouse:ウェルビーイングなクラブハウス
- Feb 10, 2021 #21 タイでムエタイ修行:タテキ刑務所に連れていかれるの巻
- Feb 12, 2021 #22 Clubhouse:初対談は弱点克服
- Feb 13, 2021 #23 Clubhouse:食とWellbeingを禅と科学から考える
- Feb 14, 2021 #24 プライベート:お食い初めで親バカのタテキ
- Feb 15, 2021 #25 Clubhouse:バイオハッキングな対談実現!
- Feb 16, 2021 #26 Clubhouse:殺生はしないがセッションはした
- Feb 18, 2021 #27 Clubhouse:全てはRelationshipが大事なのかな
- Feb 19, 2021 #28 子育て:子連れ狼になるのか?
- Feb 21, 2021 #29 ライブ配信:実験失敗&新番組の告知
- Feb 22, 2021 #30 Clubhouse:第三弾も勢いありすぎでした…
- Feb 23, 2021 #31 子育て:アメリカ産休短いよ・・・
- Feb 25, 2021 #32 GETT:「黄金の経験」EP12のイントロ
- Feb 26, 2021 #33 Clubhouse:ガチンコファイトクラブハウスその1
- Feb 28, 2021 #34 どのツラ下げて戻ってきたぁ?
- Mar 1, 2021 #35 clubhouse:ツイッターのフィードがウンコまみれでスイマセン
- Mar 2, 2021 #36 子育て:抱っこしながら収録あんぎゃー
- Mar 3, 2021 #37 子育て:抱っこしながら仕事からのレスリングおつ
- Mar 4, 2021 #38 レターに回答: 質問のレベル高いっす
- Mar 6, 2021 #39 ブラジル:ファベーラでボクシング
- Mar 7, 2021 #40 タテキッチン:オイルマリネがハンパねぇ
- Mar 8, 2021 #41 国際女性デー:世界中の女性に敬礼ぃぃぃ!
- Mar 10, 2021 #42 プライベート:春が近いのに最近の冷水シャワーがヤバい件…
- Mar 11, 2021 #43 ボストン:311あれから10年
- Mar 12, 2021 #44 Clubhouse:いや、そりゃ腹減るよ、、、
- Mar 13, 2021 #45 タテキッチン:日本から食べる瞑想をボストンに輸入
- Mar 14, 2021 #46 プライベート:自然保護区でバードウォッチング
- Mar 15, 2021 #47 Clubhouse:「SNSが体内に与える影響」の話を終えて...
- Mar 16, 2021 #48 Clubhouse:ちょっとした必要とされる感がプチ幸せ
- Mar 17, 2021 #49 プライベート:戦うダディーの愚痴
- Mar 18, 2021 #50 Clubhouse:警察OBと最強部隊を最後尾に集結させた部屋
- Mar 19, 2021 #51 プライベート:日本の桜を17年みてないのか(泣)
- Mar 21, 2021 #52 プライベート:久しぶりのコテンパン状態…
- Mar 23, 2021 #53 プライベート:今週も濃い予定で埋まっているぜ
- Mar 23, 2021 #54 プライベート:宿題してたら感謝の凄さに更に気づく
- Mar 25, 2021 #55 Clubhouse:誰かベホマ唱えて、、、ぐふぅ
- Mar 26, 2021 #56 プライベート:ニアミスゴメス
- Mar 26, 2021 #57 プライベート:バーチャル花見でお腹いっぱい
- Mar 28, 2021 #58 プライベート:着物de寿司
- Mar 29, 2021 #59 プライベート:痒いところに手が届いた日曜日
- Mar 30, 2021 #60 プライベート:廻り回ってその恩恵は巡ってくる
-
TEKトーク
3
- Jan 14, 2026 TEK TALKs はじめました
- Jan 21, 2026 インフレという名の「見えないパンチ」と、ボストンで感じる生存本能
- Jan 27, 2026 極寒ボストンで「世界一美味いチョコ」を食べて、アテンション(関心)について考えた
-
イベント
4
- Aug 20, 2025 マインドバレー アムステルダム 2025
- Oct 9, 2025 Hololife VIPディナー東京2025
- Oct 12, 2025 ホロライフサミット東京2025
- Oct 15, 2025 朝は温泉で「静」を、夜はビートボックスで「動」の瞑想を体験した一日
-
スケッチ
2
- Dec 19, 2016 マイク大工原 -do it now, think later-
- Apr 23, 2017 今すぐスケッチ!後で考えろ!
-
バイオハッカーサミット
19
- Jun 1, 2022 Optimized Day ワークショップ 2022 ヘルシンキ
- Jun 2, 2022 VIPディナー ヘルシンキ 2022
- Oct 12, 2022 Optimized Day ワークショップ 2022 アムステルダム
- Oct 14, 2022 VIPディナー アムステルダム 2022
- Oct 17, 2022 バイオハッカーの旅 Amsterdam 2022
- Sep 3, 2023 サブカルなトンネル: アフターパーティーとロンドン滞在
- Oct 24, 2023 Optimized Day ワークショップ 2023 アムステルダム
- Oct 26, 2023 VIPディナー アムステルダム 2023
- Nov 4, 2023 バイオハッカーのクロニクル: アムステルダム 2023
- Jun 30, 2024 OPTIMIZED DAY ワークショップ 2024 ヘルシンキ
- Jul 1, 2024 VIPディナー ヘルシンキ 2024
- Jul 4, 2024 バイオハッカーサミット2024ヘルシンキ: チームジャパンと10周年記念
- Jul 6, 2024 オフサイトイベント サムライアイランド 2024 ヘルシンキ
- Jun 11, 2025 ホロライフバイキングアカデミー -エストニアでリトリート-
- Jun 13, 2025 ホロライフディナー:食事で生物学をアップグレード
- Jun 15, 2025 長寿ゴールドラッシュ:ホロライフサミット2025
- Jun 18, 2025 次世代ウェルネス戦略:ホロライフマスターマインド
- Oct 9, 2025 Hololife VIPディナー東京2025
- Oct 12, 2025 ホロライフサミット東京2025
-
ヒオちゃん
15
- Jul 26, 2015 Rio 1 -ヒオちゃんとの出会い-
- Aug 2, 2015 Rio 2 -巣立ちトライアル-
- Sep 17, 2015 Rio 3 -水浴び 飛行訓練 サーフィン-
- Oct 24, 2015 Rio 4 -ひたすら突く-
- Dec 27, 2015 Rio 5 -ヒオちゃんと爆睡-
- Mar 3, 2016 Rio 6 -猫のような雀-
- Apr 6, 2016 Rio 7 -タテキの頭で砂浴び-
- May 19, 2016 Rio 8 -ヒオちゃん爆睡-
- May 29, 2016 Rio 9 -ネイルサロン・タテキ-
- Jul 5, 2016 Rio 10 -ヒオちゃんと読書-
- Sep 25, 2016 Rio 11 -ヒオちゃんとの日常-
- Nov 17, 2016 Rio 12 -放し飼い-
- Nov 27, 2016 Rio 13 -完全休養-
- Apr 21, 2017 Rio 14 -ツンデレ-
- Jul 17, 2019 ヒオちゃんに姉・妹・兄・弟?
-
プライベート
74
- Aug 27, 2018 テクノロジーの電源を抜く
- Feb 27, 2019 Kamakura ボストン
- Jun 1, 2019 15年
- Jun 16, 2019 弟ボストンくる
- Aug 11, 2019 タングルウッド ボストン交響楽団 2019
- Aug 18, 2019 テクノロジーの電源を抜く 2019
- Dec 28, 2019 アーサーと再会!世界とつながる
- Jan 11, 2021 TEK Talks はじめました
- Jan 20, 2021 #2 タイでムエタイ修行:ロードワークに行く時はイシツブテを忘れずに
- Jan 21, 2021 #3 北米MMA:汚い話ですいません…試合会場はなんと…!
- Jan 22, 2021 #4 ブラジルで柔術修行:地球の裏側で○光中毒にされそうになった話
- Jan 23, 2021 #5 どうやってジゼル・ブンチェンのトレーナーになった? タノジョー砲炸裂...
- Jan 24, 2021 #6 パラグアイに寄り道:半袖短パンのおっちゃんの装備がチートすぎる件
- Jan 25, 2021 #7 スペイン:山奥のダウンタウンで野宿した後お湯に感動した話
- Jan 27, 2021 #8 フランス:ムーランルージュにて賄賂で解決…
- Jan 28, 2021 #9 フィンランド:ラップランドの迷いの森で全員凍死ゲームオーバー?
- Jan 29, 2021 #10 イタリア:心臓バクバクでヴェスパを返却
- Jan 31, 2021 #11 香港:重慶大厦(チョンキンマンション)に泊まる
- Feb 1, 2021 #12 タテキッチン:誕生日フルコース年に一度のペスカトーレ
- Feb 2, 2021 #13 アメリカ:イタリア人街でハイタッチのタイミングを外した訳
- Feb 3, 2021 #14 アルゼンチン:干城のアナザースカイ「悪魔の喉笛」
- Feb 4, 2021 #15 NesPicks:森喜朗氏「女性が…」発言について
- Feb 5, 2021 #16 ポッドキャスト収録後:みんな息吐こうぜ!
- Feb 6, 2021 #17 Clubhouse:逆カルチャーショックを乗り越える
- Feb 7, 2021 #18 Clubhouse:セクシー女優の部屋で大人の保健の話
- Feb 7, 2021 #19 スーパーボウル:日本にトムの凄さが伝わってほしい
- Feb 9, 2021 #20 Clubhouse:ウェルビーイングなクラブハウス
- Feb 10, 2021 #21 タイでムエタイ修行:タテキ刑務所に連れていかれるの巻
- Feb 12, 2021 #22 Clubhouse:初対談は弱点克服
- Feb 13, 2021 #23 Clubhouse:食とWellbeingを禅と科学から考える
- Feb 14, 2021 #24 プライベート:お食い初めで親バカのタテキ
- Feb 15, 2021 #25 Clubhouse:バイオハッキングな対談実現!
- Feb 16, 2021 #26 Clubhouse:殺生はしないがセッションはした
- Feb 18, 2021 #27 Clubhouse:全てはRelationshipが大事なのかな
- Feb 19, 2021 #28 子育て:子連れ狼になるのか?
- Feb 21, 2021 #29 ライブ配信:実験失敗&新番組の告知
- Feb 22, 2021 #30 Clubhouse:第三弾も勢いありすぎでした…
- Feb 23, 2021 #31 子育て:アメリカ産休短いよ・・・
- Feb 25, 2021 #32 GETT:「黄金の経験」EP12のイントロ
- Feb 26, 2021 #33 Clubhouse:ガチンコファイトクラブハウスその1
- Feb 28, 2021 #34 どのツラ下げて戻ってきたぁ?
- Mar 1, 2021 #35 clubhouse:ツイッターのフィードがウンコまみれでスイマセン
- Mar 2, 2021 #36 子育て:抱っこしながら収録あんぎゃー
- Mar 3, 2021 #37 子育て:抱っこしながら仕事からのレスリングおつ
- Mar 4, 2021 #38 レターに回答: 質問のレベル高いっす
- Mar 6, 2021 #39 ブラジル:ファベーラでボクシング
- Mar 7, 2021 #40 タテキッチン:オイルマリネがハンパねぇ
- Mar 8, 2021 #41 国際女性デー:世界中の女性に敬礼ぃぃぃ!
- Mar 10, 2021 #42 プライベート:春が近いのに最近の冷水シャワーがヤバい件…
- Mar 11, 2021 #43 ボストン:311あれから10年
- Mar 12, 2021 #44 Clubhouse:いや、そりゃ腹減るよ、、、
- Mar 13, 2021 #45 タテキッチン:日本から食べる瞑想をボストンに輸入
- Mar 14, 2021 #46 プライベート:自然保護区でバードウォッチング
- Mar 15, 2021 #47 Clubhouse:「SNSが体内に与える影響」の話を終えて...
- Mar 16, 2021 #48 Clubhouse:ちょっとした必要とされる感がプチ幸せ
- Mar 17, 2021 #49 プライベート:戦うダディーの愚痴
- Mar 18, 2021 #50 Clubhouse:警察OBと最強部隊を最後尾に集結させた部屋
- Mar 19, 2021 #51 プライベート:日本の桜を17年みてないのか(泣)
- Mar 21, 2021 #52 プライベート:久しぶりのコテンパン状態…
- Mar 23, 2021 #53 プライベート:今週も濃い予定で埋まっているぜ
- Mar 23, 2021 #54 プライベート:宿題してたら感謝の凄さに更に気づく
- Mar 25, 2021 #55 Clubhouse:誰かベホマ唱えて、、、ぐふぅ
- Mar 26, 2021 #56 プライベート:ニアミスゴメス
- Mar 26, 2021 #57 プライベート:バーチャル花見でお腹いっぱい
- Mar 28, 2021 #58 プライベート:着物de寿司
- Mar 29, 2021 #59 プライベート:痒いところに手が届いた日曜日
- Mar 30, 2021 #60 プライベート:廻り回ってその恩恵は巡ってくる
- Apr 28, 2024 ボストン日本祭り 2024
- May 10, 2024 ヴェロニカがボストンに来た話
- Jul 10, 2024 北欧でワーケーション
- Jul 1, 2025 タリンからヘルシンキへ:家族が教えてくれたこと
- Oct 16, 2025 1000年前のシルク(十二単)を着て、東京で一番汚くて安いラーメン屋へ行った日
- Oct 20, 2025 百薬:1000年の発酵と感謝が出会う場所
- Jan 1, 2026 令和8年 謹賀新年
-
ボストン
4
- Apr 26, 2019 ボストン日本協会ガラディナー
- Apr 27, 2019 MAPS 2019 ガラディナー
- Jul 28, 2019 タイムアウトマーケット
- Aug 4, 2019 ボストンスカイラインの眺め
-
旅行
11
- Oct 31, 2019 VIPディナー ヘルシンキ 2019
- Nov 4, 2019 初めてラップランドに行ってきた
- Nov 5, 2019 ヘルシンキ 2019
- Sep 3, 2023 サブカルなトンネル: アフターパーティーとロンドン滞在
- Mar 18, 2024 SXSW2024
- Apr 7, 2024 イビサ島でバイオハッカーズリトリート2024
- Jul 6, 2024 オフサイトイベント サムライアイランド 2024 ヘルシンキ
- Jul 10, 2024 北欧でワーケーション
- Jul 21, 2024 チェコ共和国 2024
- Jul 1, 2025 タリンからヘルシンキへ:家族が教えてくれたこと
- Oct 14, 2025 野沢温泉:東京サミット後のリカバリー
-
日本
8
- Sep 7, 2018 ベン=グリーンフィールド 東京滞在 #1
- Sep 9, 2018 ベン=グリーンフィールド 東京滞在 #2
- Sep 10, 2018 ベン=グリーンフィールド 東京滞在 #3
- Sep 11, 2018 ベン=グリーンフィールド 東京滞在 #4
- Oct 12, 2025 ホロライフサミット東京2025
- Oct 14, 2025 野沢温泉:東京サミット後のリカバリー
- Oct 16, 2025 1000年前のシルク(十二単)を着て、東京で一番汚くて安いラーメン屋へ行った日
- Oct 20, 2025 百薬:1000年の発酵と感謝が出会う場所